2023年12月22日

ケアマネージャー資格の難易度とは?試験の概要と合格率が低い理由も併せて解説
介護・福祉分野の資格の中でも、特に難易度が高いといわれているのが「ケアマネージャー(介護支援専門員)」です。ケアマネージャー試験の合格率は例年10~20%程度と低く、さらに近年は受験資格の厳格化により受験者数の大幅な減少が続いています。
この記事では、ケアマネージャー資格の取得難易度について、資格の取り方や試験の合格率とともに解説します。ケアマネージャーを目指している方はもちろん、介護職からのステップアップを視野に入れている方もぜひ参考になさってください。
―― ①ケアマネージャー試験の受験資格を満たす
―― ②ケアマネージャー試験を受ける
―― ③実務研修を受講する
2.ケアマネージャー試験の難易度はどのくらい?
―― ケアマネージャー試験の概要
―― 合格率の推移
―― 介護・福祉系資格の合格率と比較
3.ケアマネージャー試験の合格率が低い理由
―― 受験資格が厳格化されたから
―― 解答方式の難易度が高いから
―― 十分な学習時間の確保が難しいから
4.ケアマネージャー資格を取得するメリット
5.まとめ
1.ケアマネージャー資格を取得するまでの3ステップ
ケアマネージャーとは、介護保険制度にもとづくケアマネジメント(介護支援サービス)を実施する専門職です。ケアマネージャーになるには資格を取得し、各都道府県から介護支援専門員証の交付を受ける必要があります。
ここでは、ケアマネージャーの資格の取得に必要なステップをご紹介します。
①ケアマネージャー試験の受験資格を満たす
ケアマネージャー試験の受験資格は、下記のAまたはBの有資格者で、かつ、AおよびBの期間が通算5年以上、かつ、従事日数900日以上が必要です。
| 【A】規定の国家資格等にもとづく業務に従事する者 | 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、管理栄養士(栄養士を含む)、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、精神保健福祉士 |
|---|---|
| 【B】規定の相談援助業務に従事する者 | 生活相談員、支援相談員、相談支援専門員、主任相談支援員 |
②ケアマネージャー試験を受ける

ケアマネージャー試験は「公益財団法人 社会福祉振興・試験センター」が作成し、各都道府県が毎年実施しています。 ケアマネージャー試験に必要な実務経験は、職場に記入してもらう「実務経験証明書」の提出をもって証明します。申し込み時には業務内容や従事期間などを確認する資格審査があり、審査を通過すればケアマネージャー試験を受けることができます。
③実務研修を受講する
ケアマネージャー試験に合格した後は、各都道府県が実施する介護支援専門員実務研修を受講します。実務研修では講義と演習の形式で、ケアマネジメントにおける専門的な知識・技術を習得します。 実務研修の修了後に介護支援専門員の登録申請をおこない、都道府県からの介護支援専門員証の交付をもってケアマネージャーの実務に従事できるようになります。
2.ケアマネージャー試験の難易度はどのくらい?
数ある介護・福祉関連資格の中でも特に難関といわれるケアマネージャー試験。
ケアマネージャー試験の難易度はどのくらいなのか、試験の概要と合格率の推移をご紹介します。
ケアマネージャー試験の概要
ケアマネージャー試験(介護支援専門員実務研修受講試験)は全60問で構成、ほとんどの都道府県がマークシート方式を採用しています。
試験の出題内容と問題数は次のとおりです。
○介護支援分野:25問
○保健医療福祉サービス分野:35問
試験の難易度によって異なりますが、合格ラインは6~7割程度といわれています。
合格率の推移
ケアマネージャー試験の合格率・受験者数・合格者数の推移をまとめました。| 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | |
| 第1回(1998年度) | 44.1% | 207,080人 | 91,269人 |
| 第2回(1999年度) | 41.2% | 165,117人 | 68,090人 |
| 第3回(2000年度) | 34.2% | 128,153人 | 43,854人 |
| ~ | ~ | ~ | ~ |
| 第14回(2011年度) | 15.3% | 145,529人 | 22,332人 |
| 第15回(2012年度) | 19% | 146,586人 | 27,905人 |
| 第16回(2013年度) | 15.5% | 144,397人 | 22,331人 |
| 第17回(2014年度) | 19.2% | 174,974人 | 33,539人 |
| 第18回(2015年度) | 15.6% | 134,539人 | 20,924人 |
| 第19回(2016年度) | 13.1% | 124,585人 | 16,281人 |
| 第20回(2017年度) | 21.5% | 131,560人 | 28,233人 |
| 第21回(2018年度) | 10.1% | 49,332人 | 4,990人 |
| 第22回(2019年度) | 19.5% | 41,049人 | 8,018人 |
| 第23回(2020年度) | 17.7% | 46,415人 | 8,200人 |
参考:厚生労働省|第23回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について
第1回ケアマネージャー試験が実施されたのは1998年。初期の合格率は30~40%程度と特段難易度の高い資格ではありませんでしたが、回数を重ねるにつれて低下していき、ここ10年は10~20%程度の合格率となっています。
また、2018年度は受験資格変更の影響を受けたことで受験者数が大きく減少し、合格率は過去最低となりました。しかし、2019年度以降は受験資格変更以前と同程度の合格率に戻っているようです。
なお、2021年度のケアマネージャー試験(2021年10月10日実施)は全国で54,334人が受験しています。受験資格が厳格化された2018年度以降、受験者数が5万人を超えるのは初めてでした。
介護・福祉系資格の合格率と比較
ケアマネージャー資格と他の介護・福祉系資格の合格率を比較しました。なお、各資格の合格率は2021年10月末時点で公表されている直近のものです。| 第23回 | ケアマネージャー | 17.7% |
|---|---|---|
| 第33回 | 介護福祉士 | 71.0% |
| 第33回 | 社会福祉士 | 29.3% |
| 第110回 | 看護師 | 90.4% |
| 第56回 | 作業療法士 | 81.3% |
| 第56回 | 理学療法士 | 79.0% |
【参考】:
厚生労働省|第23回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について
厚生労働省|第33回介護福祉士国家試験合格発表
厚生労働省|第33回社会福祉士国家試験合格発表
厚生労働省|第107回保健師国家試験、第104回助産師国家試験及び第110回看護師国家試験の合格発表
厚生労働省|第56回理学療法士国家試験及び第56回作業療法士国家試験の合格発表について
介護福祉士の合格率は例年30%前後ですが、他の介護・福祉系資格は70~90%程度あります。ケアマネージャー試験の難易度は、他の資格の合格率と比較してみても格段に高いといえるでしょう。
3.ケアマネージャー試験の合格率が低い理由
他の介護・福祉系資格と比較しても合格率が低く、難易度の高さが際立つケアマネージャー試験。
ここではケアマネージャー試験の合格率が低い理由について、具体例を挙げながらご紹介します。
受験資格が厳格化されたから
ケアマネージャー試験の受験資格は2015年に見直しがおこなわれ、経過措置後の2018年度から現行の受験資格が適用されました。以前は介護業務で実務経験を満たすことができましたが、2018年度からは「規定の国家資格に基づく業務経験5年」または「相談援助業務経験5年」のいずれかを満たす必要があります。
2018年度以降の受験者数がグッと落ち込んだことから、受験資格の厳格化によってケアマネージャー資格の取得難易度がさらに上がったといえるでしょう。
解答方式の難易度が高いから
ケアマネージャー試験の解答方式には「五肢複択」が採用されています。ケアマネージャー試験では1つの問題に選択肢が5つあり、正しいものを2つもしくは3つ選ぶ方式となっています。
五肢複択は選んだ選択肢がすべて合っていなければ得点できず、1つでも間違っていればその問題は0点となってしまいます。難易度の高い五肢複択の解答方式は、ケアマネージャー試験の合格率を下げる要因になっているといえるでしょう。
十分な学習時間の確保が難しいから
ケアマネージャー試験を受けるには、規定の国家資格または相談業務に関する5年以上の実務経験が必須です。そのため、この受験資格を満たすためには働きながら資格取得を目指す人が多くなっています。
家事や育児など家庭の用事と両立させている受験者も多く、十分な勉強時間の確保が難しいため、合格率が低い要因のひとつになっていると考えられます。
4.ケアマネージャー資格を取得するメリット

ケアマネージャーは難易度の高い資格ですが、ケアマネージャーとしての実務ができるようになれば以下のメリットが得られます。
○仕事の幅や活躍の場が広がる
○給料アップが期待できる
○ワークライフバランスが整った働き方が実現できる
介護サービスの利用者が自立した生活を送れるよう、ケアマネージャーにはケアマネジメントを通してサービスの提供側と利用側をつなぐ重要な役割が任されます。
また、ケアマネージャーは他の介護・福祉系資格と比べ給与水準が高めなこと、基本的に夜勤がなく体力面の負担が少ないこともメリットといえるでしょう。
5.まとめ
ケアマネージャー試験の合格率は10~20%程度が続き、他の介護・福祉系の資格と比べても難易度の高い資格といえます。
2018年度からは受験資格が厳しくなり、介護業務の実務経験では要件を満たせなくなりました。また、ケアマネージャー試験の独特な解答方式も合格率が低い要因になっていると考えられます。
しかし、ケアマネージャーの資格があれば仕事の幅が大きく広がり、職場の待遇やワークライフバランスの改善も見込めるようになります。
難易度は高めですが、資格を取得するメリットは大きいでしょう。介護や福祉の分野で幅広く活躍したい方は、ケアマネージャー資格の取得を目指してみてはいかがでしょうか。
介護21コラム記事監修者
株式会社アドバン
人材採用サポート・Web事業・印刷物制作を中心とする事業を展開する株式会社アドバンを1991年に設立。人材採用サポートの中でも、医療・介護業界に特化する専門求人サイト『医療21』『介護21』を運営。リアルな求人情報を届け、人材紹介ではない”ベストマッチングの場”を提供している。

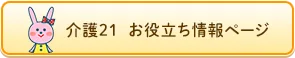



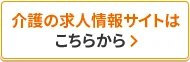
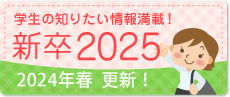


 職種資格から求人を探す
職種資格から求人を探す